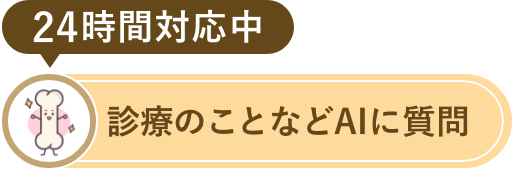骨粗鬆症の原因

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は、骨の強度が低下して骨折しやすくなる疾患です。
「沈黙の病気」とも呼ばれるほど、自覚症状が乏しく、気づかないうちに進行していることも少なくありません。
そのため、発症前の予防や早期発見がとても大切です。
骨がもろくなる仕組み
私たちの骨は、常に「骨リモデリング」と呼ばれる新陳代謝を繰り返しています。
これは、古い骨を壊す「骨吸収」と、新しい骨をつくる「骨形成」のバランスによって成り立っています。しかし、このバランスが崩れ、骨吸収のスピードが骨形成を上回る状態が続くと、骨密度が低下し、骨の内部構造(骨質)も劣化してしまいます。
その結果、骨がもろくなり、骨折しやすくなるのが骨粗鬆症です。
骨粗鬆症の2つのタイプ
骨粗鬆症は原因によって、2つのタイプに分類されます。
原発性骨粗鬆症
加齢やホルモンの変化、生活習慣などが原因となるもっとも一般的なタイプです。骨粗鬆症患者の多くはこちらに該当します。
続発性骨粗鬆症
病気や薬の影響で骨密度が低下するタイプです。基礎疾患の治療と同時に、骨粗鬆症への対応も必要となります。
原発性骨粗鬆症の主な原因
加齢
年齢を重ねることで骨形成の力が衰え、骨密度は徐々に低下します。骨密度のピークは20代に達し、それ以降は加齢とともに減少していきます。
ホルモンの変化
特に女性は、閉経によってエストロゲン(女性ホルモン)が急激に減少します。エストロゲンには骨吸収を抑える働きがあるため、その減少が骨のもろさにつながります。男性でも、加齢に伴うテストステロンの減少が影響することがあります。
遺伝的な体質
家族に骨粗鬆症を患っている人がいる場合、自身も発症リスクが高くなることが知られています。遺伝的な体質を持つ方は、特に早めの予防が重要です。
栄養不足
骨の健康に必要な栄養素
| カルシウム | 骨の主成分 |
|---|---|
| ビタミンD | カルシウムの吸収を助ける働き |
| ビタミンK | 骨形成に関わるたんぱく質の活性化に必要 |
これらの栄養素が不足すると、骨の形成が不十分になり、骨粗鬆症のリスクが高まります。
運動不足
骨は適度な刺激(負荷)によって強くなります。運動不足が続くと骨に十分な刺激が伝わらず、骨密度が低下してしまいます。特に、歩く・立つなどの体重をかける運動は、骨の健康にとって重要です。
不適切な生活習慣
日々の習慣が、知らず知らずのうちに骨に悪影響を与えていることがあります。
喫煙
タバコを吸うことで骨への血流が悪くなり、骨をつくる細胞の働きも低下します。
過度のアルコール摂取
アルコールを多くとると、骨形成が抑えられたり、カルシウムやビタミンDの代謝に悪影響を及ぼしたりすることがあります。
カフェインのとりすぎ
コーヒーやお茶の飲みすぎは、体内のカルシウムを排出しやすくする可能性があります。
続発性骨粗鬆症の主な原因
疾患によるもの
次の病気により、骨密度が低下することがあります。
- 甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患
- 慢性腎臓病、肝疾患、COPDなどの慢性疾患
- 糖尿病、動脈硬化といった代謝性疾患
- 関節リウマチなどの炎症性疾患
- 吸収不良症候群、胃の切除後などの消化器疾患
- 神経性食欲不振症などの栄養障害
薬剤によるもの
次の薬剤を長期使用している場合、骨密度が低下することがあります。
- ステロイド薬
- 抗てんかん薬
- 抗うつ薬
- ワーファリンなどの抗凝固薬
- メトトレキサート(免疫抑制薬)
- 一部の利尿剤
- など
薬の影響が考えられる場合には、医師と相談しながら骨の健康を守る対策をとることが大切です。
骨粗鬆症は、さまざまな要因が複雑に関係して発症する病気です

年齢や体質といった避けられない要因もありますが、生活習慣や栄養、運動などによって予防できる部分もたくさんあります。
尼崎市のまえだ整形外科リウマチクリニックでは、骨密度検査や生活指導を通じて、骨粗鬆症の早期発見・予防・治療をサポートしています。
気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。