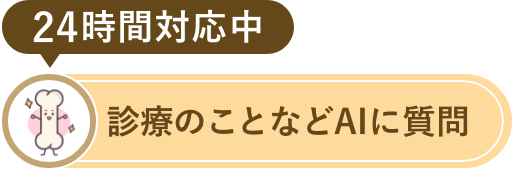骨粗鬆症の治療(薬物療法)
骨粗鬆症は、適切な治療によって
骨折リスクを大きく減らせる病気です。
まえだ整形外科リウマチクリニックでは、患者さまの状態や生活スタイルに合わせ、最適な薬物療法をご提案しています。
骨粗鬆症治療薬の種類
骨粗鬆症の薬は大きく「骨吸収を抑える薬」と「骨をつくる薬」に分かれます。その他、骨の代謝を助ける補助的なお薬もあります。
骨吸収抑制薬
骨を壊す細胞(破骨細胞)の働きを抑えて、骨密度の低下を防ぐ薬です。
ビスフォスフォネート製剤
| 代表薬剤 (商品名) |
アレンドロネート(フォサマック®)、リセドロネート(ベネット®)、ミノドロン酸(ボナロン®など) |
|---|---|
| 特徴 | 骨吸収を抑制し、骨折予防効果が高い標準治療薬 |
| 投与方法 | 内服(週1回・月1回)、点滴(年1回) |
| 主な副作用・注意点 | 胃腸障害(胃痛・逆流)、顎骨壊死、非定型大腿骨骨折 |
抗RANKL抗体
| 代表薬剤 (商品名) |
デノスマブ(プラリア®) |
|---|---|
| 特徴 | 強力に骨吸収を抑える。半年に1回で管理が容易 |
| 投与方法 | 皮下注射(6か月ごと) |
| 主な副作用・注意点 | 低カルシウム血症、治療中断後の急速な骨密度低下 |
※治療を中断すると骨密度が急激に低下するため、継続管理が大切です。
SERM(選択的エストロゲン受容体モジュレーター)
| 代表薬剤 (商品名) |
ラロキシフェン(エビスタ®)、バゼドキシフェン(ビビアント®) |
|---|---|
| 特徴 | 女性ホルモン様作用で骨密度を維持 |
| 投与方法 | 内服(毎日) |
| 主な副作用・注意点 | 血栓症リスク(長期臥床・既往歴のある方は注意) |
骨形成促進薬
骨をつくる細胞(骨芽細胞)の働きを活発にし、新しい骨を増やす薬です。
副甲状腺ホルモン(PTH)製剤
| 代表薬剤 (商品名) |
テリパラチド(フォルテオ®、テリボン®) |
|---|---|
| 特徴 | 骨形成を促進し、骨密度を増加 |
| 投与方法 | 自己注射(毎日または週2回) |
| 主な副作用・注意点 | めまい、吐き気、高カルシウム血症。 使用は最長2年(骨肉腫リスク上昇の可能性があるため) |
抗スクレロスチン抗体
| 代表薬剤 (商品名) |
ロモソズマブ(イベニティ®) |
|---|---|
| 特徴 | 骨形成を促進しつつ骨吸収も抑制する二重作用 |
| 投与方法 | 皮下注射(月1回) |
| 主な副作用・注意点 | 注射部位の反応、まれに心血管イベント。使用は最長12か月 |
その他の治療薬
活性型ビタミンD3製剤
| 代表薬剤 (商品名) |
エルデカルシトール(エディロール®)、アルファカルシドール(ワンアルファ®) |
|---|---|
| 特徴 | カルシウム吸収を促進し、骨の石灰化を助ける |
| 主な副作用・注意点 | 高カルシウム血症に注意 |
カルシウム製剤
| 特徴 | 骨の主成分を補う。不足時に内服で補充(基本は食事から摂取) |
|---|---|
| 主な副作用・注意点 | 過剰摂取で便秘や尿路結石のリスク |
注射治療のメリット
注射による治療には、以下のようなメリットがあります。
- 内服薬よりも効果が強力で確実
- 週1回、月1回、半年に1回など投与間隔が長く、服薬忘れの心配が少ない
- 医師の管理下で行うため、治療効果や副作用を安全に確認できる
- 胃腸障害など、内服薬で起こりやすい副作用が少ない
注射治療が向いている方
- 過去に骨折を経験した方
- 内服薬で副作用が出た方(特に胃腸障害など)
- 毎日の服薬が難しい方
- 短期間で骨密度改善を目指したい方
- 高齢で飲み忘れが心配な方
- 重度の骨粗鬆症の方
特に「過去に骨折がある」「内服で副作用が出た」「高齢で服薬が難しい」方には注射治療が適しています。
当院の治療方針
まえだ整形外科リウマチクリニックでは、2025年改訂の最新骨粗鬆症診療ガイドラインに基づき、患者さまの状態に応じた薬物療法をおこなっています。
- 骨折リスクに応じた最適な薬の選択
- 内服薬と注射薬の両方の選択肢を提示
- 定期的な骨密度検査で効果を確認
- 副作用のモニタリングときめ細かなケア
さらに、薬だけでなく栄養指導・運動療法・生活習慣改善を組み合わせ、患者さまが無理なく続けられる治療を大切にしています。
骨粗鬆症は、早く気づけば防げる病気です

「薬が必要かどうか」「どの治療が自分に合うのか」と迷う方も、ぜひお気軽にご相談ください。
尼崎市・阪急園田駅1分にあるまえだ整形外科リウマチクリニックは、地域の皆さまの骨の健康を守り、健康寿命をのばすために全力でサポートします。